学習塾新潟市秋葉区・江南区・南区 個別指導新潟市秋葉区
学習塾五泉市 学習塾阿賀野市 学習塾阿賀町
新津駅前校の教務課です。
高校生の定期テストも終了して、夏休みも迫ってきています。当社は完全1対1の個別指導、さらには学生ではなく厳選されたプロ教師による指導となりますから、担当をする教師にも限りがあります。今年はおかげさまで生徒数も例年より多いため、教師の残りの空き時間が少なくなってきました。受講を検討されている方は、早目の教育相談の予約を推奨します。
また、KATEKYO学院・新津駅前校では、中学3年生対象の夏期講習として、『夏の特訓教室』を開催いたします。学力別1クラス8名程度までの少人数、高校入試対策の授業になります。 KATEKYO自慢のプロ教師が担当します。定員に達した場合は、申込を締め切らせていただきます。お早目のお申込をお勧めいたします。
KATEKYO自慢のプロ教師が担当します。定員に達した場合は、申込を締め切らせていただきます。お早目のお申込をお勧めいたします。
【内 容】
科 目:国語、数学、英語、社会、理科の5科目
時 数:60分×3コマ×8日
料 金:36,300円(消費税・テキスト代込)
日 程:7月29日(木)~8月7日(土)、8月1日(日)、8月4日(水)はお休み 計8日間
時間割:①ベーシッククラス(まだ余裕はあります)
1限9:10~10:10、2限10:20~11:20、3限11:30~12:30
②ハイレベルクラス(定員まで残りわずか)
1限13:30~14:30、2限14:40~15:40、3限15:50~16:50
お問い合わせは、下段(PCの場合は上段)の✉お問い合わせをクリックいただくか、下記までお電話をください。
新津駅前校・新津事務局
☎ 0250-23-6699

 英語リーディング問題の解法を
英語リーディング問題の解法を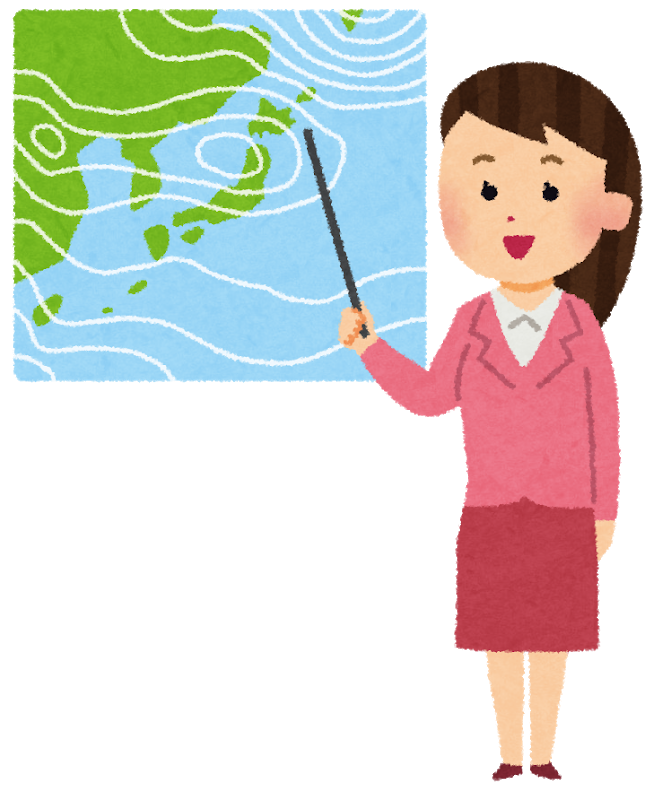 その他には、フェーン現象も暑くなる原因です。このフェーン現象に関しては最近、発生のメカニズムが地域によっては考えられていたものと違うことが、筑波大の研究によって明らかになりました。
その他には、フェーン現象も暑くなる原因です。このフェーン現象に関しては最近、発生のメカニズムが地域によっては考えられていたものと違うことが、筑波大の研究によって明らかになりました。
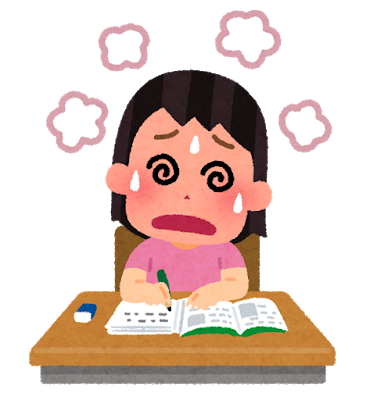
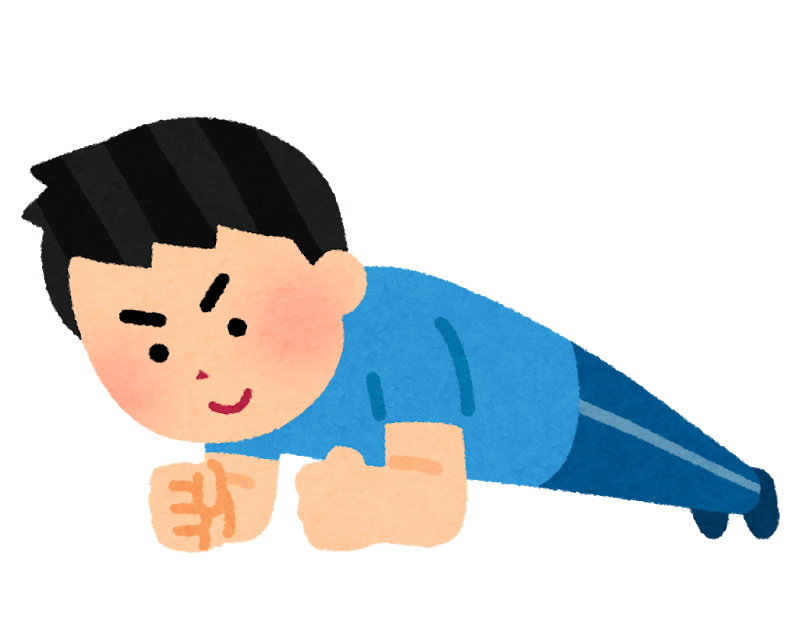 やっている方が多いですが、本当にそれでよいのでしょうか?
やっている方が多いですが、本当にそれでよいのでしょうか? 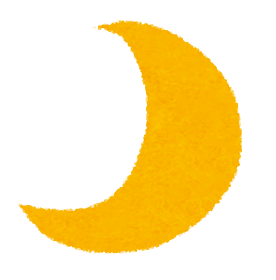 天気が良ければ午前中はうっすらと見えていたりするのが下弦の月。これからどんどん細くなっていく月ですね。
天気が良ければ午前中はうっすらと見えていたりするのが下弦の月。これからどんどん細くなっていく月ですね。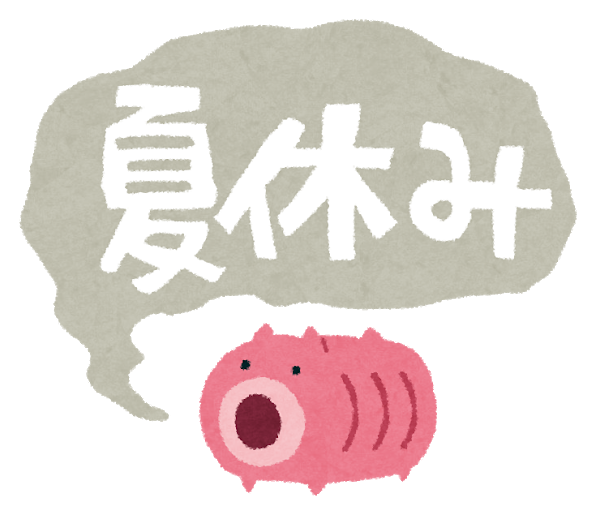 「夏休みに勉強いっぱいするぞ!」という気持ちの人も多いかと思います。夏休み中のことはさておいて、夏休み前にできることとは何でしょうか?
「夏休みに勉強いっぱいするぞ!」という気持ちの人も多いかと思います。夏休み中のことはさておいて、夏休み前にできることとは何でしょうか?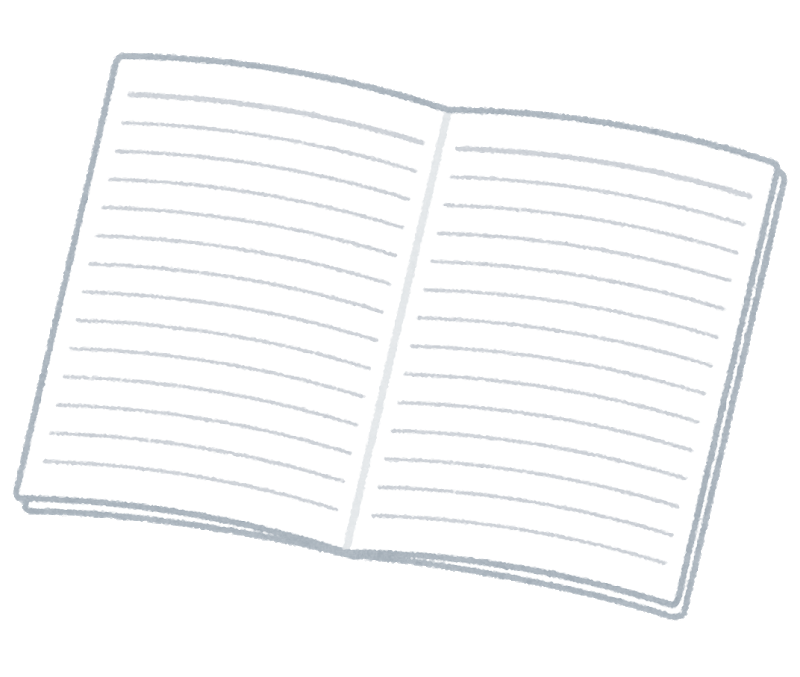 見開きの2ページ、英語の日本語訳ノートなら、4・5行間隔で本文を書くようにアドバイスしています。
見開きの2ページ、英語の日本語訳ノートなら、4・5行間隔で本文を書くようにアドバイスしています。